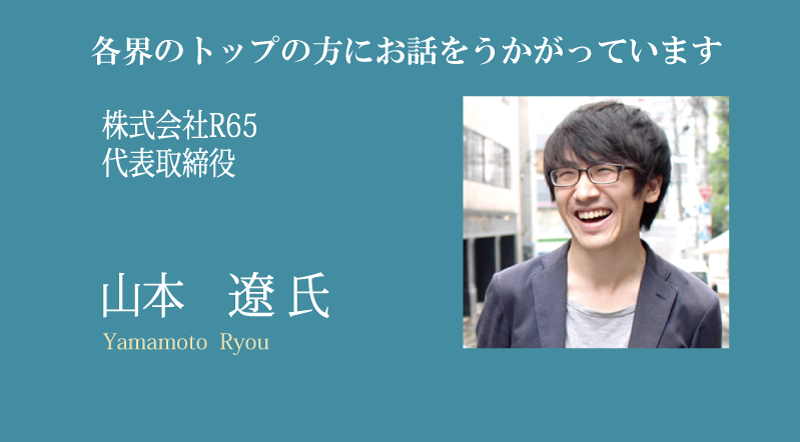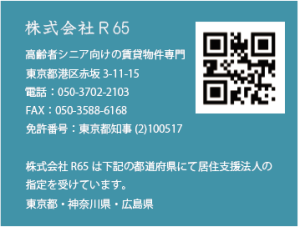色彩トップインタビュー
株式会社R65 代表取締役 山本 遼氏に、ヨシタミチコ理事がお話を伺いました。
元気で一人暮らしできる65歳を
「高齢者」でひとくくりにしたくない。
ヨシタ 「R65不動産」という名前が印象的ですね。どういう意味が込められているのですか。
山本 「R65不動産」は65歳以上の方を対象にした賃貸住宅の紹介サービスで、介護施設や高齢者施設を紹介するものとは違います。「株式会社高齢者住宅」とか「シニア不動産」のようにしてしまうと、高齢者介護のようなイメージになってしまうので、あくまでも65歳以上の賃貸という意味で、R65不動産という名前にしました。
お客様として来られる方は、年齢は65歳以上ですが、身体的にも気持ちの面でも若い方が多いんですね。賃貸の一人暮らしで十分やっていける方がたくさんいらっしゃいます。ですから、高齢者というイメージでくくるよりも、シンプルに「65歳以上」を意味する「R65」と名づけました。
ヨシタ 65歳以上の4人に1人が賃貸住宅への入居拒否を経験しているというデータがあるそうですね。
山本 そうなんです。一人暮らしでなくても、また、しっかりした保証人がいても難しい場合がありますし、自宅を売却した現金をお持ちでも、支払い能力に問題がなくても物件が見つからないこともあります。
今までは、夫婦でもダメ、息子さんや娘さんが保証人になってもダメ、現金や資産を持っていてもダメという感じで、一律に70歳以上には貸さないというケースが多かったのです。ただ、最近少しずつですが、不動産業界でも意識が変わってきているように思います。
65歳以上が入居可能な賃貸物件は、
全体の約5%しかありません。
ヨシタ 高齢者の賃貸契約が難しいのは、孤独死などが起こる可能性が高いからではないかと思います。
山本 「賃貸」と聞くと、学生や若い単身の人が借りるものというイメージがすごく強いのですが、現在、賃貸に住んでいる高齢の方は400万世帯もあるんですね。これは全高齢者の6人に1人が賃貸ということになります。若いころから賃貸で、気づいたら高齢になっていたというような方もいらっしゃいますが、そういう方の場合も契約更新ができないなどの問題が出ています。
日本では少子高齢化が非常に急激に進んだことと、バブル期に建てられたものが築40年を迎えて再開発される時期になっていることが重なって、65歳以上の方が賃貸契約をしにくいという問題が起きていると考えられます。
ヨシタ このような問題は都市部に多いのでしょうか。
山本 いいえ。都市部に限ったことではありません。例えばもともと住んでいたところが坂の多い地形の土地ですと、車がないと生活が非常に不便です。しかし、高齢になって免許を返納したら、その場所では暮らしていけないため、駅の近くに賃貸を借りたいという需要もあるのです。
国土交通省の調査によると2015年~2020年の5年間の間に賃貸に引っ越した人のうち3割は、もともと持ち家があった人であることがわかりました。先ほどお話しした傾斜地の問題もありますし、庭などの手入れができなくなったなど、さまざまな理由で持ち家を手放す人もいるわけです。つまり、家を持っているから賃貸に住まないというわけではないのです。
家族に看取られて亡くなっても事故物件はおかしい。
ヨシタ やはり、高齢者の賃貸契約の場合、亡くなった後のことが気になりますよね。後始末をきちんとできるのかどうか、それを引き受けるような組織や仕組みが必要になると思います。
山本 そうですね。僕が事業を始めたのは2015年なのですが、当時から高齢者に部屋を貸している大家さんでも、実際に何が起こるのかをよくわかっていないということがありました。もちろん、高齢者に部屋を貸していない大家さんは何が起こるのかわからないし、漠然と怖いと思っているれど、何が怖いのかをきちんと理解できていなかったと思います。
そんな状況からだんだんわかってきたことは、孤独死の問題、家賃の滞納、亡くなった後の荷物を誰が片づけてくれるのかということが問題の中心だということなのです。
僕の祖母は家族に看取られながら最期を迎えましたが、では、その家は事故物件なのかといえば、そうではないと思います。これに関しては定義がなかったのですが、2020年に国のガイドラインが出て、「自然死で人が亡くなった住宅は事故物件ではない」と定義されました。もちろん、早く見つけてあげることは、とても重要になっていると思います。

監視ではない見守りの仕組みが必要です。
ヨシタ トイレなどにセンサーをつけて、1日のうちのトイレ使用頻度で業者が駆けつけるという仕組みなどもありますね。
山本 これまでは見守りと言いながら監視感の強いものが多かったんですね。今、うちのサービスで好評なのが、電気のスマートメーターと連動するシステムで、3年前から提供しています。
あまりに電気を使っていない状態だと「おかしいな」ということで、まず本人に連絡がいき、本人が出なければ家族に連絡がいくようになっています。これは、電力会社と一緒に仕組みを考えました。行政からも引き合いがきたりしています。月々数百円で利用できるので、大家さん、入居者さん、どちらが負担するにしても利用しやすいと思います。工事もいりませんし、カメラなどもないのでプライバシーも守られて、安価でというところが評価されています。
ヨシタ 実際に、その通報で亡くなっているのが見つかるということもあるんでしょうか。
山本 はい。もちろんありますが、そこまでいかないケースも多くて、例えば1泊の旅行に行っていたとか、入院していたというケースもあります。入院などの場合ですと、入院当日にご本人が電話に出られないこともあるため、連絡がつかずに現場に行ってみたら本人がいないということもあり、ケアマネジャーさんに連絡して入院だったとわかったという例もあります。ただ、こうやってすぐに異常を察知できるようにしておくことで、大家さんの不安も解消できますし、仮に亡くなったとしてもすぐに発見できるというのが、最大のメリットだと思います。

契約書をしっかり作っておけば、居住支援法人が遺ったものを整理できます。
ヨシタ スマートフォンに入った情報などをはじめ、急に亡くなったら情報処理に困るものもありますね。
山本 遺されたものは、洋服1枚でも資産になってしまいます。単純に相続しようとしても、相続人がたくさんいる場合、すべての相続人に連絡をとらなければならないなど手続きが非常に煩雑です。
そのため、賃貸契約をする時に、賃借人の死後に「残置物の処理」や「残置物の換価や指定先への送付」、「賃貸借契約の解除」ができる「高齢者入居向けの賃貸借契約書」を作り、僕らが居住支援法人として残置物処理や契約解除まで請け負う契約をしてもらうということをしています。こうすることで、大家さんも、借りる人も安心して賃貸契約をしてもらえるようになったと思います。
ヨシタ 今日は興味深いお話をありがとうございました。