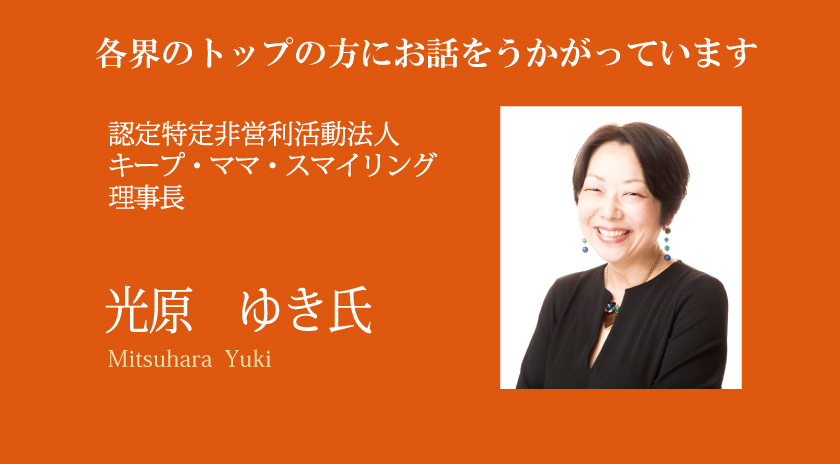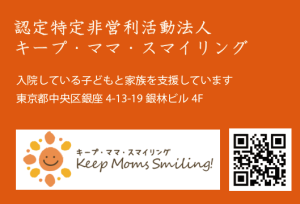色彩トップインタビュー
病気の子どもを育てる人への支援活動をおこなう団体「認定NPOキープ・ママ・スマイリング」代表理事 光原ゆき氏に、ヨシタミチコ理事がお話を伺いました。
最初の子どもが生後間もなく入院して、
初めて「付き添い入院」の実態を知りました。
ヨシタ 入院する子どもの家族を支援するという現在の活動を始められたきっかけは、何だったのですか。
光原 私自身の経験がもとになっています。35歳の時に長女を出産しましたが、生まれたその日に救急車で大学病院に運ばれて、生後5日で手術を受けました。その後、私自身も産科を退院して子どもの入院している大学病院に行きましたが、看護師さんから「お母さんも一緒に泊ってください」と言われました。そこで初めて、子どもが入院したら親が付き添うものだということを知りました。それまでは、「付き添い入院」という言葉も知りませんでした。
その時体験した親の付き添いの現実というのが、まるで看護師さんの仕事を肩代わりするようなものだったのです。もちろん治療行為はできませんが、薬を飲ませたり、ミルクを飲ませるのも親の仕事です。ミルクを飲ませるといっても、うちの子の場合、鼻から胃に管を入れなければならないのです。管がちゃんと胃に届いているか、おなかに聴診器を当てて確認してからミルクをセットします。さらに、一日にどれだけ飲んだかということも、親が記録をつけなければなりません。そんな風にとても忙しいのが付き添い入院なのですが、本来、これはおかしなことなのです。
入院時の患者の生活に関することは、看護料として医療報酬に含まれていますから、その仕事を付き添いの親が担うのは間違っています。ただ、看護師一人当たりの受け持ち患者数は、大人の患者も子どもの患者も同じなのです。例えば、一般的には、夜勤の看護師さんが1人で10人の患者さんを見るのですが、これが赤ちゃんだったらどうでしょう。1人で一度に10人の赤ちゃんの世話はできませんよね。そのため、付き添いの親にその仕事が回ってくるという構図になっています。

「付き添い生活応援パック」 カラフルなボックスが気持ちを明るくしてくれる。
親の付き添いが必須という病院もあります。
いつ食事を買いにいけるかもわかりません。
ヨシタ どの病院でも付き添いが求められるのですか。
光原 今のところ、付き添いのルールは病院によってまちまちというのが現状です。家族の付き添いは、泊りは絶対ダメという病院もあれば、大学病院などでは人手が足りないので、子どもの入院に親の付き添いは必須となっているところも多いのです。
長女はいくつかの病院に入院しましたが、ある病院では付き添いの人の食事は自分で用意しなければならないため、子どもが眠ったすきをみつけては、院内の売店に走りました。次にいつ買いにいけるかわからないので、何食分も買ったりして…。別の病院では、有料で付き添い用の食事が出るところもあり、そのときはとても助かりました。
長女はその後無事に退院することができましたが、数年後、次女が出産前に難病であることがわかりました。生後すぐにくつかの病院で治療を受け、一時は自宅から遠くはなれた病院まで行ったりもしたのですが、11ヶ月の時に急変して亡くなってしまったのです。
短い一生でも娘が生まれてきた意味を
形にしたいという思いで活動を始めました。
ヨシタ そうでしたか。それはショックだったでしょう。とても深い悲しみですね。
光原 はい。突然、娘をなくして、目の前が真っ暗になりました。一ヶ月ほど仕事も休んで、娘の写真を見ては泣いてばかりいました。でも、しばらくするうち、彼女は短い一生であったけれども、意味があって生まれてきてくれたんだと思うようになりました。そして、彼女が私のところに来てくれたから知ることができたこと、体験できたことで、何か社会の役に立つ活動がしたい。それが彼女がこの世に生まれてきた証になるんじゃないかと思いました。
私にできることは何かと考えた時に、娘二人の付き添いの経験が思い出されました。いくつもの違う病院での付き添いの経験があったので、付き添い家族の過酷な環境を知っていました。そこで、現在の活動を立ち上げたのです。
ヨシタ 「付き添い」の問題には、小児医療が置かれている問題も同時にあると思います。
光原 そうですね。私も長女の入院の際に、私自身が高熱で倒れてしまって、病院にいられなくなったことがあったんです。でも、熱が下がって病院に戻ってみたら、娘は一回り小さくなってやせてしまっていて、私と目も合わせられないような状態になっていました。「これはたいへんだ!」とびっくりして、親が倒れるわけにはいかないんだと思いました。
でも、その時にドクターや看護師さんを恨む気持ちにはならなかったんです。というのも、「先生って、いつ家に帰っているのかな?」と思うほど医師は長時間労働でしたし、看護師の置かれている状況も非常に過酷なものだというのを、付き添い中に見て知っていたからです。医療者の皆さんは子どものために全力を尽くしてくださっている。でも人手が足りないのは、制度がそもそも間違っているんだなと感じました。

付き添いの方へ提供する食事を調理中。
病児を支援する団体はあっても、
付き添う親を支援する団体はありませんでした。
ヨシタ 入院付き添いの家族のためのお弁当サービスなど、さまざまな家族支援をおこなっていますね。
光原 これまで病気の子どもを支援する団体はあっても、親をメインに支援する団体はなかったと思います。病気と闘っている子どものためには、やはり近くにいる親の存在が非常に大切です。そばにいて、手を握ったりする家族がいることがとても大事なのに、医療ではそこが抜け落ちてしまいます。
ですから、私たちは何とか付き添う親御さんたちの力になる方法を考えようと、まずは食事の提供から始めました。私自身が付き添いの際に一番困ったのも食事だったからです。今では累計8,800食以上を提供しています。
全国3,000人規模の実態調査で、
ようやく国が動き出しました。
ヨシタ 支援だけでなく、実態調査をもとにした提言、国への要望書の提出など、社会変革のための活動も盛んにおこなっていらっしゃいます。
光原 この問題を国に知ってもらい、医療制度自体を変えていかないと病院も動かないですから、付き添い当事者への実態調査を行ってデータを可視化しました。
「付き添い生活応援パック」という支援物資を配付する活動が3,000人を超えたあたりで実態調査を行ったところ、病院から付き添いを強要されたり、看護師の仕事を付き添いの親が肩代わりしている実態が明らかになり、そのデータを昨年、付き添い環境改善に向けた要望書とともに厚生労働省とこども家庭庁に提出しました。
嬉しいことに、すぐにこども家庭庁で検討会が開かれ、医療機関に対する実態調査が始まりました。厚生労働省もすぐに動いてくれて、今年度の診療報酬改定に見守りや付き添い者の食事や睡眠などへの対策が盛り込まれました。また、看護助手や保育士を充てることに対して診療報酬の加算が認められました。

ヨシタ 今までの活動の成果が現れた訳ですね。
光原 日本小児科学会でも、付き添い環境に関するワーキンググループができました。治療の観点からも、小児医療の現場では親の付き添いが大事であるということや、家族の事情に合わせて付き添うかどうかの選択ができること、付き添う場合は、付き添い家族の環境をよりよくしなければならないなど、私たちが要望したことに寄り添う内容の見解が発表され、とても心強く感じています。
ようやく当事者と医療者との目線が合った気がしています。また、こども家庭庁では、この付き添い問題についての来年度予算に概算要求が出ましたから、今後は付き添い環境の改善にも予算がついていくと思います。
ヨシタ これからの動きに期待が持てますね。
今日は興味深いお話をありがとうございました。